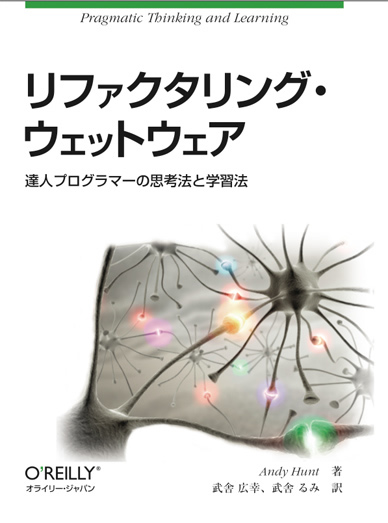訳者あとがき
まず目に焼き付いたのは「ハッピーマック」だった。
一九八六年七月、私は米国ニューヨーク州の田舎町イサカにあるコーネル大学の図書館でマッキントッシュの前に座っていた。九月からの留学生活に備えて英語研修プログラムに参加していたのだ。毎日英語のレポートを書くことになっており、研修生仲間が「図書館にマッキントッシュがあって誰でも使える」という情報を仕入れてきたので、それではさっそく私も使ってみようと思ったわけだ。
アルバイトの学生のいる受付で「マックライト」というワープロソフトとシステムの入ったフロッピーディスクを借り、マッキントッシュのスイッチを入れた。するとあのにこにこ顔が登場する。話には聞いていたが本当にかわいいコンピュータを作ったものだ。
マックライトを起動する。「なるほど、マウスを二回押すだけでいいのか。簡単だな」テキストを入力する。「自動的に改行してくれるのか。たいしたもんだ」
しかし驚いたのはそれからだ。「これは書名だから...イタリックはできないよなあ。下線なら引けるかな。なになにスタイルでいいのかな?」「うゎ、こりゃ参った。簡単にイタリックになっちまう。太字もできる! 大きさも自由自在か」
それまで大学の研究室でパソコンより値段も高く処理速度も速いワークステーションを使っていた私にとって、それは新鮮な驚きだった。ワークステーションのUNIX(ユニックス)も捨て難いが、「一般の人」にUNIXが使えるとも、必要だとも思えない。UNIXの出来の悪い(良い?)子供のようなMS-DOS(エムエスドス)も同様。それに比べてマッキントッシュはどうだ。こんなに直感的に操作ができるコンピュータは見たことがない。
この経験で、本書の著者と同じようにマッキントッシュの虜になってしまった。妻に「マックペイント」というお絵書きソフトを見せて丸め込み、米国生活の必需品の車も買わずに学生割引で当時の最上位機種(といってもこれしかなかった)マックプラスを早速購入した。統合ソフトのJAZZ【ルビ/ジャズ】(本文には使い物にならないと書いてあるが家計簿をつけるぐらいのことはできた)、描画ソフトのスーパーペイント、音楽ソフトのコンサートウェア、ゲームなどを大学のコンピュータストアや通信販売で購入しては楽しんだ。そして翌年、HyperCard(ハイパーカード)というまったく新しい型のソフトウェアが発売された。情報の整理法を根底から変えてしまうようなソフトウェアだった。「なぜこうも次々と我々を驚かせるものが出せるのか。アップルで働いているのはどんな連中なのだ」そう首を傾げたものだ。
この疑問は本書の翻訳でほぼ完璧に解決された。これまでにも様々な本でマッキントッシュの開発の経緯については読んだことがあったが、マッキントッシュを主人公にしたものには出会わなかった。本書は誕生前の種が蒔かれた段階から、IBM、モトローラとの共同開発によるPowerPC(ワーピーシー)という強力な子孫にバトンタッチし、純正マックとしての十年余の生涯をほぼ終えようとしている現在までの、マッキントッシュの歴史全体を覆うものである。著者の十年を超えるマッキントッシュとのつき合いの集大成ともいえる。原著は米国のベテラン雑誌記者の本らしく機知に富んだきびきびとした筆致で書かれており、文芸翻訳の経験のない私にはかなりハードな翻訳となった(おまけに「マックワールドエキスポに間に合わせましょう」という時間的制約も加わった)。しかし、第一章からビンビンと心に響く熱い言葉が登場人物の口から発せられ、次第に本書の世界にのめり込んでいった。まるで私自身の考えや経験を語ってくれているように思えるところが随所に出てくるのだ。一種運命的な感じさえした。「おまえ、最近たるんでいるぞ。少しは考えろ」と誰かにいわれているような気がした。
実は規模はまったく比べ物にならないが、私にも似たような経験があったのだ。もう十年も前のことになってしまうが、当時小さなソフトウェア会社でワークステーションを使ってかなり大きなソフトウェアの開発をしていた。プロジェクトの構成員は全部入れても十人に満たないほどだったが、実に面白い人たちの集まりだった。世の中の他の人がどう思うかではなく「どうするのが正しいと我々が思うか」で開発を進めていった。私自身もそれまでの自分の経験がすべて生かせる分野で、楽しくて仕方がなかった。朝から終電にぎりぎり間に合う時間まで、夢中になって働いた(残業手当はまったくつかなかった)。
当時は回りを見る余裕もあまりなく、研究に未練の残っていた私は、一年で会社を辞め大学に戻ってしまった。そのソフトウェアは紆余曲折を経て二つに別れ、そこで働いていた人々もばらばらになってしまったが、二つとも今も生き残っている(勤めていた会社の方はつい先日合併によりその名前もなくなってしまった)。そしてマッキントッシュを含む各種のパソコンで動くソフトウェアとなって「一般の人々」の手元に届くようになった。
一方、研究者の道を歩もうとした私は徐々に「どうも違う」と思い始めた。会社にいてソフトウェアを作っていたときの方が充実していたようにも思えてきたのだ。それを決定的にしたのは留学の経験だった。「ものを作って一般の人に使って欲しい。そして、ものを作るのならば大学ではなく民間企業だ」これが私の出した結論だった。スティーブ・ジョブズの言葉を少し引用させていただきたい。
「お役所が大仰にことを興さなくたって、社会に大きな影響を与えることは民間企業でもできる。むしろ民間企業の方がその影響力は大きいかもしれない。僕も、エジソンと電球の方がマルクスなどよりはるかに大きく世界を変えたと言う意見に賛成だ。エジソンと同じことができる千載一遇のチャンスがここ五年のうちに巡ってくるんだよ」
マッキントッシュを開発した人々は何回ものピンチを切り抜けながらこのチャンスをしっかりとつかみ取った。我々の回りに、現代の日本に、このようなチャンスは巡ってくるのだろうか。私は既に小さいのを一度逃してしまっている。
* * *
原著の世界を、登場人物の熱い思いを、翻訳を通してどの程度忠実に読者にお伝えできたか不安だが、限られた時間の中で最善の努力をしたつもりだ。自分の専門の分野であるので、技術的な内容はコンピュータの専門家でない方々にもお解りいただけるよう、日米の事情の違いにも留意してできるだけわかりやすく、私自身の言葉を使って表現するよう心がけた。これが達成されているかどうかは読者の皆さんの判断におまかせしたい。
本書の翻訳の機会を与えてくださったのは、株式会社翔泳社編集部の三輪幸男さんである。三輪さんとは大学の(互いに顔だけは知っていた)同窓生なのだが、不思議なご縁があっていままで様々なお仕事させていただいてきた。このような本を私にご紹介くださって本当に感謝している。翻訳中にもさまざまな面でお世話になった。重ねてお礼を申し上げたい。斎藤恵美氏、有限会社シグマインターナショナルには本書の一部の翻訳をお手伝いいただいた。ここにお礼を申し上げる。もっとも、当然のことながら私自身で確認をし、私の調子に改めたので最終的な責任は私にある。最後に、私の会社の翻訳部の武舎るみ氏には特に日本語の表現に関して数多くの改善点を指摘してもらい、また、疑問点に関して相談にものってもらった。ここhttp://localhost/www.marlin-arms.com/support/insgrt/に感謝したい。
「真のアーティストは製品を世に送り出すのだ」そして、送り出した後は人々の評価を待つしかない。
1994年1月22日
マッキントッシュの公式発表からちょうど十年目の日に
訳者 武舎広幸
 マーリンアームズ
マーリンアームズ